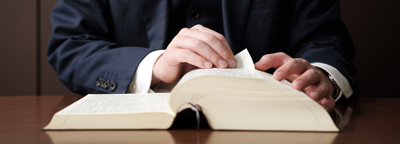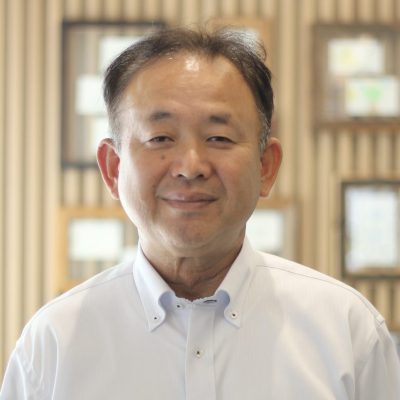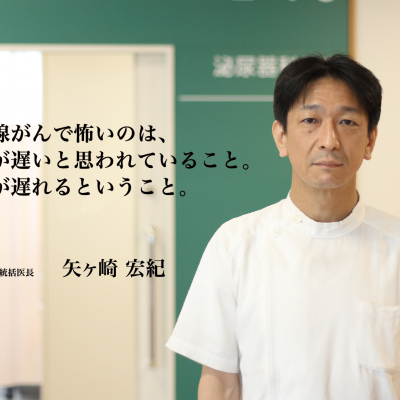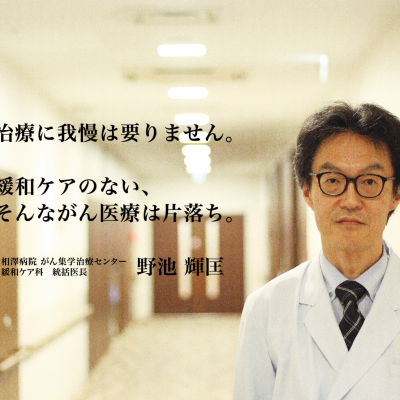「はじまり」の今昔
▼目次
1.「スタート合図」の今昔
2.「一日の始まり」の今昔
3.隅に置けない人とは

1.「スタート合図」の今昔
日本人にとってスタートのかけ声と言えば「位置について、用意、ドン」ですが、このかけ声は日本の文化として脈々と受け継がれてきたものではありません。昭和2年、日本陸上競技連盟がスタートの合図となる競技用語を一般に募集し、突如誕生したものです。
それ以前は、スタートのかけ声はバラバラでした。例えば「いいか。ひぃ、ふぅ、みぃ」と言ってから、旗を降ろすことがスタートの合図だったりと、地域によって全く異なっていました。
2.「一日の始まり」の今昔
昔の西洋では、多くの地域が日没を一日の始まりとしていました。旧約聖書の創世記・1章5節にも「夕べがあり、朝があった」と書かれています。
その風習は今でも残っています。クリスマスは12月25日なのに、その前夜の24日をクリスマス・イヴとして大々的にお祝いします。「イヴ」は「evening」と同義の古語「even」が語源となっていて、一日は前夜の日没から始まるという習慣をキリスト教が受け継いだからです。つまり24日の夕方は、昔は25日の始まりだったのです。
また、日本語の「あした」は、現代では「翌日」を意味しますが、古語では「朝」を示します。ですから、ひょっとすると日本でも、日没を一日の始まりとしていたのかもしれません。
3.隅に置けない人とは
このように、原点であるはずの「はじまり」ですら、時代によって変化します。そして、変化の後に訪れるのは、いつでも新しい「はじまり」です。
物事は何でも、初めから上手くなどいきません。「はじめは恥目」です。物事の初め、始まりこそ、恥をかくべきタイミングです。知ったかぶりほど、後悔することはありません。
命長ければ恥多し、とも言います。はじに置けない人(隅に置けない人)になるためにも、恥を恐れず、初めてのことにも「始める」勇気を持ち続ける人間でありたいものです。