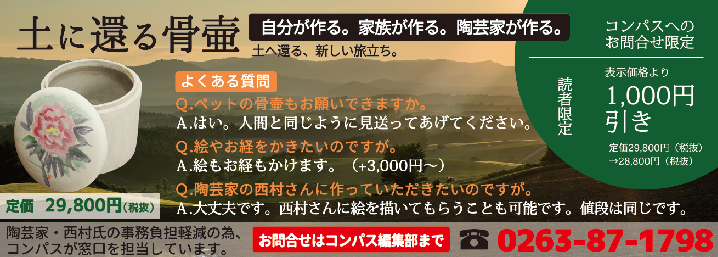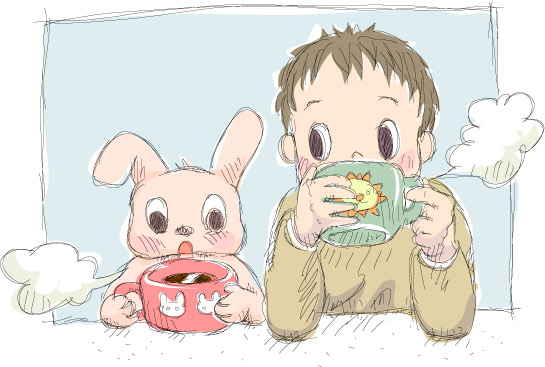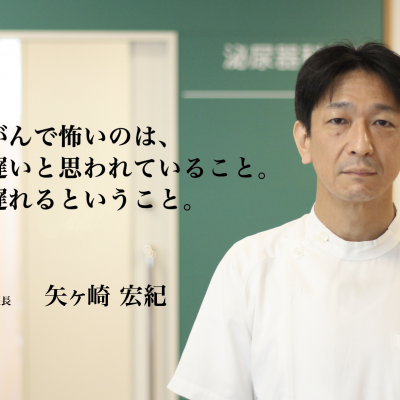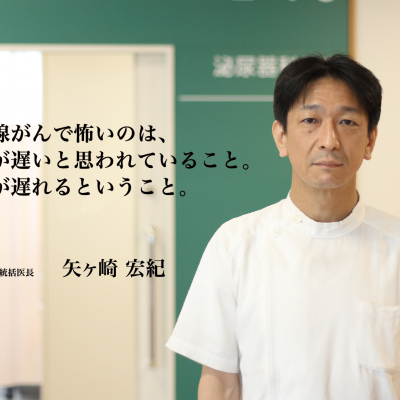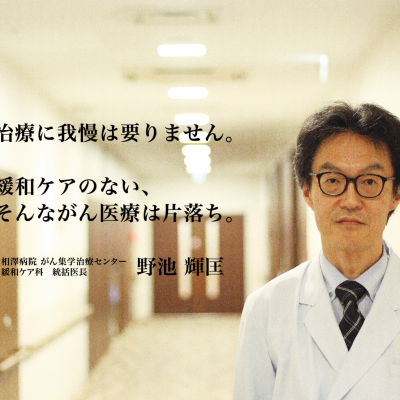フリーペーパー「コンパス」【連載小説】 幸せのコンパス(第3話)
日向穂志は、北を指さない不思議なコンパスを持っています。では、そのコンパスはどこを指すのか。それは、掌に乗せた人が願っているものの在り処です。日向は、そんなコンパスを使って、困っている人を導いていきます。
フリーペーパー「コンパス」でお馴染みの連載小説「幸せのコンパス」をお楽しみください。
——登場人物—————
日向穂志(ひなたほし):僕。主人公。北ではなく、幸せの方角をさすコンパスを持つ。
日向月子(ひなたつきこ):主人公の妻。
長田将大(ながたまさひろ):ながた寿司の店主。保志・月子と同級生。40歳。
後藤 一樹(ごとう かずき):巨大企業「後藤建設」の長男。通称・ゴッド。
濱 源治(はま げんじ):気品漂う老紳士。
——————————–

「僕の頭に傷がある?いったい何の話なんだ?」
僕が驚いて訊ねると、ゴッドはそんな僕に驚いた。
「自分のことだろ?本気で言っているのか?」
「本気も何も、知らないものは知らない」
僕がそう答えると、ゴッドは〝信じられない〟という表情をして言った。
「稲妻みたいに大きな傷跡だぞ。また忘れてしまったのか?」
「また?」と僕がいぶかしむと、ゴッドは急に話題を変えた。
「まあ、忘れたならどうでもいいや。それより、ちょっと付き合えよ。どうせ暇だろ?」
それで僕は頭に来た。
「どうでもいいことないだろう。頭の傷だぞ?それに、そもそも僕は暇じゃない。仕事がある」
「そうか。じゃあ急がないとな」
「どうしてそうなるんだ」
「まぁそう言うな。十年ぶりなんだ。付き合えよ」
そうやって、結局、僕はゴッドに付き合わされた。昔からそうだった。彼はどんなことでも自分の思い通りに事を運び、欲しい物は何でも手に入れた。だから、彼が僕のコンパスに頼ったことはない。多分、これからもそうだと思う。神は何でも手に入れる。そして、ゴッドはこれからも、きっとゴッドのままだろう。
連れて行かれたのは「カフェ・ソーダ」というお店だった。ゴッドの後輩が経営していて、その彼が「曽田」という苗字だったから、ゴッドが「ソーダ」と名付けたらしい。そんな彼の店は、木の素材を活かした雰囲気がとてもお洒落で、ほんのり漂う木の香りが心地よかった。カフェの割には広く、色々なところに観葉植物や流木があった。ただ、曽田は木は好きなのだろうが、ソーダには関心がないようだった。壁には今っぽく加工された写真付きメニューがたくさん張り出されていたが、店名でもあるソーダはなかった。
僕らがカウンターに腰掛けると、彼はカウンターにいた若い先客を紹介してきた。
「うちの常連です。二年前からほぼ毎日、ここのカツ丼を食べに来てくれるんです」
「へぇ」とゴッドが頷くと、若者は立ち上がり、僕たちに挨拶をした。
「初めまして、小柳です。愛知県出身の信濃大学二年、二十歳です」
ゴッドはおどけて言った。
「愛知出身でも、みそカツ以外のカツを食べるんだな」
「はい」小柳は学生らしく、はつらつと返事をした。「でも、実はぼく、どちらかと言えば魚の方が好きなんです。特にこっちに移住してからは、信州サーモンが一番好きです」
「信州サーモン?」
「信州ブランドの魚です。ニジマスとブラウントラウトを交配させた、サーモンのような魚です」
「要するに、サーモンの偽物ね」
「いいえ。れっきとしたサーモンです」
その口調からは強い熱意が感じられ、ゴッドは圧倒されたのか、サーモン談義を中止して話を戻した。「それにしても、ここのカツ丼がそんなに旨いとは知らなかった」
「食べたことないんですか?本当に美味しいですよ」小柳は目を輝かせ、言った。「でも、美味しいだけじゃないんです。ここのカツ丼はとても縁起がいいんです」
「縁起がいい?」
「はい」小柳は元気よく頷いた。「二年前の受験の前日、ここでカツ丼を食べながら勉強のおさらいをしていたんです。すると、その時の内容がびっくりするほど本番の試験で出題されて……おかげで見事合格できました」
「さすが日本の勝負飯」
「でも、まだあるんです」小柳は止まらなかった。「ぼく、入学してすぐ、ある女の子に一目惚れしたんです。そして、その子に告白する直前にもここのカツ丼を食べたんですけど、やっぱり上手くいきました」
「そうなると、今日もいいことがありそうだ」
「そうですね」と、小柳は首を縦に振ったが、その返事はわずかに暗かった。「今日、母親がぼくに会いに来るんです。そして、ここで一緒に食事をすることになっているんですが、それが何事もなく終わればいいなと、今はそう思っています」
「母親と飯を食うだけだろ?」
「ええ。でも、色々とありまして……あっ、来た」
その言葉で、僕たちは一斉に振り返った。そして、店の扉へ目をやった。そこには僕らと同じくらいの年齢の、上品な女性の姿があった。随分と若いお母さんだな。と、僕は心の中で驚いた。けど、一番驚いたのは、小柳の第一声だった。彼は母親に近寄ると、お辞儀をしながらこう言った。「ご無沙汰しています、佳子さん」
それを聞いたゴッドは、ため息まじりに言葉を漏らした。
「今の二十歳はすごいな。俺には自分の母親を名前で呼ぶなんて、到底できない芸当だけどな」
それは僕も同感だった。お互いを名前で呼び合う親子もいる。そんな話をテレビで見たことはあったが、しかし実際にそれを目の当たりにすると、さすがにすんなりとは受け入れられなかった。
「これが〝最近の若い奴は〟ってやつか」と、ゴッドが苦笑いして言うと、曽田が静かに否定した。
「それは違いますよ、ゴッドさん」そして、小さな声で言った。「あの二人は親子ですけど、血は繋がっていないんです」
ゴッドが返事をしないでいると、曽田は続けた。
「どうやったら”お母さん”と呼べるか。それが小柳の悩みなんです」
ゴッドが無言だったこともあって、僕はひたすら黙って二人を眺めていた。彼らは僕たちから少し離れたテーブルに、向かい合って座っていた。ここからでは会話の全部を聞き取ることはできなかったけど、そのおおよそは想像できた。母は気を遣うあまり、何でもないことをとりとめもなく話し、息子は特別な会話をしようとするも、ネタが見つからなくて喋れない。見ている限りではそんな感じで、久しぶりの親子の会話は明らかに弾んでいなかった。
そんな状況が十五分ほど続き、いい加減、僕もやきもきしてきた頃だった。ようやくゴッドが口を開いた。
「なあ、曽田。ちょっと小柳をこっちへ連れてこれないか」
「えっ」と、曽田が言葉に詰まると、ゴッドは間髪入れず言った。
「返事はハイかイエスだろ?」
「でも……」
「でも?とにかく連れてこい。な?」
こうなると誰にも手が付けられない。それは曽田もわかっていて、彼はしぶしぶ二人のテーブルへ向うと、小柳だけを連れてきた。
ゴッドは目の前に小柳を立たせると「呼び出して悪いな」と言い、それから僕に向かって言った。
「なあ日向。小柳にコンパスを貸してやれないか?」
「いいよ、もちろん」と、僕は二つ返事で了承した。そして、ポケットからコンパスを取り出し、小柳の掌に乗せて、言った。「いいかい?いま、君が叶えたい一番の願いは何?それを心の中でイメージして」
小柳は非常に物わかりが良い若者だった。一瞬、不安まじりの不思議そうな顔はしたが、すぐに目をつぶると背筋を伸ばし、大きく息を吸い込むとゆっくり吐き出した。
とたんにコンパスの針は回り出した。コマのように勢い良く回り、しかし徐々にスピードを緩めると、やがてカウンターの奥の壁、メニューが張り出されている所を指して止まった。
「何なんだろう」
僕はただ首を傾げるだけだったが、ゴッドにはそのコンパスのメッセージがわかったようだった。
「なるほど」彼は頷くと、小柳に言った。「いいか、小柳。席に戻ったら、お母さんにまずこう言うんだ。一緒に食べて欲しいものがある、と。そして、カツ丼の奇跡を喋りまくれ。いいか、とにかく喋りまくれ。その間に、お前が一番食べたいと思っているものを、俺がつくってやるから。わかったな」
僕にはまるでわからなかったが、小柳は力強く頷いた。「はい」
「そうか。わかったなら戻れ。早く」
ゴッドはそう言うと、小柳を押し返した。そして、「曽田、厨房を借りるぞ」と一方的に言うと、勝手にカウンターの中に入って料理を始めた。
出来上がったその料理は、二つとも同じ海鮮丼だった。僕はてっきり奇抜なカツ丼が出てくると思っていたから、予想が外れて少し残念だった。
曽田も残念に思ったはずだ。でも、彼はそんな感情はおくびにも出さず、ゴッドに言われた通り、黙って二つの丼ぶりをテーブルへ運んだ。
僕はゴッドに訊ねた。
「なぜカツ丼ではなく海鮮丼なんだ?」
すると、ゴッドは不思議そうな顔をした。「お前は何を見ていたんだ。あれは信州サーモンといくらの……」
と、ゴッドがそこまで言ったとき、突然、小柳がこちらに向かって元気に言った。
「ゴッドさん!ありがとうございます!ぼく、頑張ります!」
その声に、ゴッドは紳士的に手で応えた。「おう」
いったい何がどうなっているのだろう。僕が小さく混乱していると、ゴッドは言った。
「お前は鈍いな。信州サーモンといくら。これって何だ?」
しかし、それでも僕がわからないでいると、ゴッドはメニューの張り出された壁を指差して、言った。
「お前のコンパスが指したのは、あれだよ。あれ」
それでようやく意味がわかった。ゴッドの指先は、親子丼の写真を指していた。
「信州サーモンといくら。これって、腹違いでも親子なんだろ?」
ゴッドはそう言うと、優しい笑みを浮かべながら立ち上がった。
「どこに行くんだよ」
僕はゴッドに訊ねたが、彼は何の返事もせず店を出た。僕は慌てて追いかけた。そして、彼の肩をつかんで振り向かせた。「ちょっと待てよ」
すると、ゴッドは冬の午後の日差しのような柔らかい顔をして、言った。
「あいつ、”お母さん”って言えるかな」その声のぬくもりは母の愛を思い出させるようで、彼の背後から降り注ぐお日様は、まるで天使たちが踊っているかのようだった。やっぱりゴッドはゴッドだな。そう思った……が、それは束の間のことだった。ゴッドはやっぱりゴッドだった。
「そんなことより、本当はお前に頼みがあって、ゆっくり話がしたかったから、あの店に行ったんだ」
突然そんなことを言われて、「は?」と僕があっけにとられていると、ゴッドは続けた。
「お前のコンパス、俺に貸してくれないか。実は、俺が帰国したのは、それが理由なんだ」
ゴッドといると、僕はいつでも混乱する。
<タイトルをクリックすると、関連記事をお楽しみいただけます>
前話 幸せのコンパス 第2話
次話 幸せのコンパス 第4話
① 幸せのコンパス 第1話
■フリーペーパー「コンパス」とは
松本市・安曇野市・塩尻市・山形村を配布エリアとした「中信版」と、長野市を配布エリアとした「長野版」の2種類があります。
フリーペーパー「コンパス」では、ウェブ版に掲載されていない、暮らしに役立つ情報もお楽しみいただけます。
■ フリーペーパー「コンパス」設置場所の検索は、こちらをクリック
■定期配本のお知らせ
コンパスは発刊が 3月 / 6月 / 9月 / 12月の末日、季刊誌です。上記にて無料で配布しております。しかし、場所によっては入手しづらいこともあり、コンパスは多数の読者様のご要望にお応えし、定期配本を始めました。配送料 2,000円/年 にて4回お届けします。
定期配本のお申し込みは、コンパス編集部 0263-87-1798 までお電話いただくかお問合せからご連絡ください。