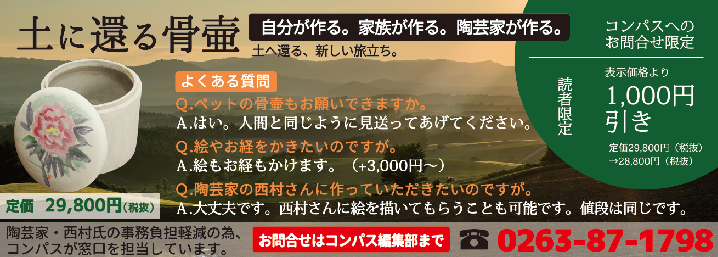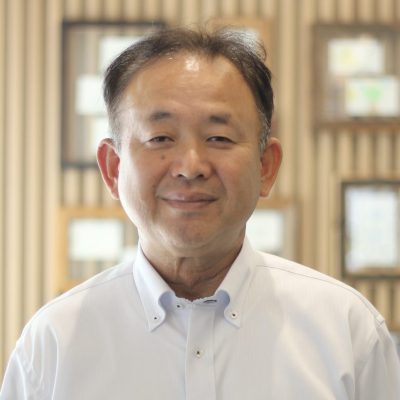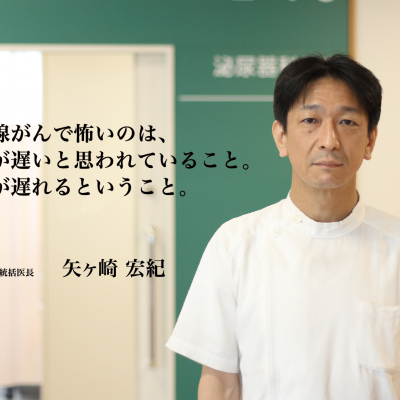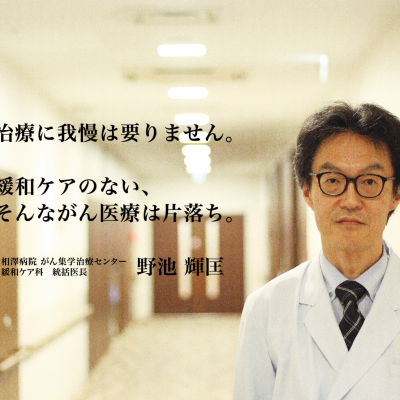フリーペーパー「コンパス」【連載小説】 幸せのコンパス(第2話)
日向穂志は、北を指さない不思議なコンパスを持っています。では、そのコンパスはどこを指すのか。それは、掌に乗せた人が願っているものの在り処です。日向は、そんなコンパスを使って、困っている人を導いていきます。
フリーペーパー「コンパス」でお馴染みの連載小説「幸せのコンパス」をお楽しみください。
——登場人物—————
日向穂志(ひなたほし):僕。主人公。北ではなく、幸せの方角をさすコンパスを持つ。
日向月子(ひなたつきこ):主人公の妻。
長田将大(ながたまさひろ):ながた寿司の店主。保志・月子と同級生。40歳。
後藤 一樹(ごとう かずき):巨大企業「後藤建設」の長男。通称・ゴッド。
濱 源治(はま げんじ):気品漂う老紳士。
——————————–

僕は毎朝目が覚めると、真っ先に歯を磨く。それは結婚した当初、朝食前に僕の口臭で妻を不快にさせたくなかったからだ。もちろん、この結婚が恋愛によるものではなく、秘密を守るための契約だとはわかっていた。それでも、僕は妻に嫌われたくなかったし、むしろもし叶うなら、彼女に振り向いてほしかった。ただ、それはもう昔の話。今の僕たちは三十路を歩き終えて四十路へ進み、もう何年も前から、完全分離型の二世帯住宅でそれぞれ別々に暮らしている。トイレもお風呂もキッチンも、それに玄関も別々。だから、僕たちが顔を合わせることは滅多にない。それでも、一度身に付いた習慣は身体にこびりついてしまったらしく、その日も僕は、起きたらすぐに歯を磨いた。そして、パンとコーヒーと林檎を食べると、もう一度歯を磨き、ながた寿司に歩いて向かった。
本音を言うと、まったく気乗りしなかった。将大はあれだけ僕のコンパスには頼らないと言っていたのに、急に翻意したからだ。いったい、彼は何を探そうとしているのだろう。僕はとても不安だった。目玉を探してほしい。そう言われたらどうしようか。僕はそんなことばかり考えていた。
というのも、実は将大の右目は義眼だった。
店に到着すると、驚いたことに濱さんがいた。昨夜この店で出会った老紳士だ。
「昨日はありがとう。とても楽しかったし、君のコンパスには心から感謝しているよ」
「こちらこそ、とても楽しかったです」僕は言った。「その上、ご馳走までしていただいて。本当にありがとうございます」
僕が丁寧に頭を下げると、ちょうどその時、視界に将大の姿が飛び込んできた。正直、ホッとした。彼はいつもと変わらなかった。右目にはちゃんと目玉があって、いつも通り白い割烹着を着ていた。
そんな安堵したての僕に、濱さんは明るく言った。
「そう言えば、君たちは後藤くんの同級生なんだってね」
「後藤くん?」
と、僕が首を傾げると、将大が言った。「ゴッドだよ。ついさっきまでここにいたんだ」
「ゴッドが?」
僕は驚いた。ゴッドは後藤建設の長男だ。実家には橋のかかったひょうたん池があって、そこで色鮮やかな鯉を何匹も気ままに泳がせている金持ちの息子だ。十年前に突然イギリスへ旅立ったが、そうか、今は日本に戻ってきているんだ。
「昨日、帰ってきたらしい」将大は言った。「なんでも、お前に会うために帰ってきた。そう言っていたけど」
「僕に?どうして?」
さあ、と将大は首をすくめた。だから僕も、その話題から離れることにした。僕は濱さんに向き直って、訊ねた。「ところで、濱さんはどうして今日ここに?」
「傘を忘れてしまってね」濱さんは言った。「君も忘れ物かい?」
「いいえ」と、僕はかぶりを振った。「僕は将大に呼び出されたんです。探し物があるんだけど、と。それも昨日の真夜中、電話で」
濱さんは笑って将大に言った。
「まあ、人生そんなものだよ。ところで、君の探し物が何なのか。それがとても気になるね」
将大はチラッと僕の方を見ると、少し居心地が悪そうに言った。
「実は、もう見つかっているんです」
え?と僕が絶句すると、将大は慌てて言葉をつないだ。
「でも、どうしても聞いてほしいんだ。自分のこと。自分の父のこと。だから少しだけ時間をくれないか?」
僕たちはイエスともノーとも言わなかった。なのに、将大はそうやって、静かに勝手に語り始めた。
自分の父は伊達政宗が好きでした。おそらく、息子の私が正宗と同じだったからだと思います。もう濱さんもお気付きかと思いますが、この右目は義眼です。私には右目の視力がありません。そして、正宗も梵天丸と呼ばれた幼少期、天然痘にかかり右目を失明しています。
そんなこともあって、父は私に自信を持たせようと、何度も伊達政宗の話をしました。本当に色々と聞かされました。ですから、自分は政宗の数々の偉業や伝説を知っています。特に好きなのは、正宗が秀吉に、一揆扇動の黒幕だと疑われた時の話です。あの時、正宗は絶体絶命の窮地に追い込まれていました。そのため、死を覚悟して黄金の十字架を用意し、白装束で上洛します。
そんな正宗に、秀吉は密書を見せつけて詰問しました。
「この手紙を見れば、謀反の首謀者がお前だと言うことは一目瞭然。この筆跡、この花押が動かぬ証拠だ」
花押は現代で言うサインのことですが、秀吉が手にしていた一揆扇動の証拠文書には、確かに正宗の花押があったのです。
が、正宗はまるで動じませんでした。それどころか平然と答えました。
「わたしの花押は鳥のセキレイを模しております。しかし、わたしはいつかこうして偽物の書類が出回ることを想定し、直筆の手紙には、セキレイの眼の部分に針で穴を開けております。わたしが今までお送りした手紙を、ぜひご覧ください。その密書が偽物であることがお分かりになるはずです」
こうして正宗は秀吉の誤解を解くことに成功した訳ですが、父はこの話をするたびにこう言ったものでした。
「やっぱり自分が自信を持って”自分のものだ”言えるものには、自他ともに認めさせるための印をつけておかなきゃな。でないと、いつか不当に偽物扱いされちまう」
本当に、あの頃の自分は正宗に心酔していました。そして、父を尊敬していました。自慢じゃないですが、自分は小学四年生の時には、漢字だらけの伊達政宗の本を読んでいました。そして、一方で寿司の修行も始めていて、皿洗いだけじゃなく寿司も包丁も握っていました。
そこで一旦、将大は語るのをやめた。ふーっ、と息をゆっくり吐き出した。が、次の瞬間「すみません、お茶も出さずに」と、慌ててそう言うと、湯のみにお茶を入れ、それを僕たちの前に差し出した。ありがとう。濱さんと僕は同時にそう言って、静かにお茶をすすった。将大もひと口お茶を飲んだ。それから少し静かな間があって、全員の口の中からお茶の渋みが消えた頃、将大は再び話し始めた。
「でも、自分が中学二年の時です。今まで寿司専門でやってきた父が、いきなり”蕎麦を始める”と言い出したんです。理由はとてもわかりやすいものでした。隣町の寿司屋が蕎麦を始めたところ、大当たりしたからでした。本当に文字通りの大当たりで、その店はたった一年の間に、何と三店舗も支店を出すに至りました。
別に今となっては、何でもないことです。寿司屋が蕎麦を始めたからと言って、握りの技術が落ちる訳ではありません。包丁さばきが下手になることもありません。でも、どうしてでしょうね。当時の私には、寿司屋が蕎麦を始めることは、なぜか本物を失うことのように思えたんです。ですから、まったく受け入れられませんでした。
そんなわけで、ある日のことです。私は父を試すことにしました。父の延し棒とそっくりの物をこしらえて、こっそりと入れ替えたんです。延し棒と言ったら、蕎麦屋が毎日使う道具です。もしそれに気付かないようなら、蕎麦なんてやめるべきだ。即刻やめさせてやる。そう意気込んでいました。
でも、本当は心のどこかで信じていました。何だかんだ言って、父は私の英雄でしたから。だから、何も気付かずに父が他界したとき、私はとても悲しくて、何だか心にぽっかり穴があいたんです」
「そうか」と、濱さんは息を漏らし、将大にポツリと訊ねた。「では、いま君が手にしている延し棒が、昨日見つかった父君の物なんだね」
しかし、将大は首を横に振った「違います」
「では、昨日見つけた延し棒はどこに?」
将大は手元の延し棒を握りしめ、答えた。「これです」
「君は何を言っているのかね」
と、濱さんが怪訝な顔をすると、将大は言った。
「この延し棒は、自分が昔から使っていた物です。でも、父の本物の延し棒でもあるんです」
「もう少し分かりやすく話してくれるかね」
はい、と将大は頷いて、言った。
「自分で言うのも何ですが、昨夜の蕎麦は過去最高の出来でした。だから、ふと父の延し棒のことを思い出し、急に触れたくなったんです。でも、隠したはずの倉庫に行っても、その探し物は見つからなかった。おかしいぞ。そう思った私は、自分の延し棒をチェックしたんです。すると、あるものが発見できました」
将大は大きく深呼吸をすると、続けた。
「我が家の家紋は、長野が発祥と言われている雁金紋です。 そして、店で使っている延し棒の両側面には、その雁金紋が刻印されています。ただ、この延し棒に限っては、雁金の目に小さな穴があいているのです」
「”この延し棒に限って”ということは、他の延し棒に穴はない?」
「はい」将大は首を縦に振った。「雁金の目に穴が開いているのは、私が持っているこの延し棒一本だけです。つまり、私が隠した延し棒を誰かが倉庫から持ち出して、反対に私が使っていた延し棒とそれを入れ替えたんです」
僕らが言葉に詰まっていると、将大がいった。
「なぜなら、こんなことをするのは父しかいないからです。つまり、自分は父が何も知らずに他界したと思っていましたが、何も知らないのは自分だったのです。私は何も気付かずに、ずっと父の延し棒を使っていたんです。」将大はそこまで話した途端、下唇が震え始め、左目に涙が貯まりだした。「しかし、話はそれで終わりません。まさか、と思って、私は昨夜、店中を見回りました。すると、すべての雁金の目にあったんです。この暖簾にも、店の外の看板にも、店内のメニューにも、全部の雁金の目に、針で開けたような小さな穴があったんです。ちょうど伊達政宗がしたように、全ての雁金の目に、小さな穴があったんです」
僕は帰りの道すがら、将大の話を思い返していた。何度思い返しても、心がほっこりして気持ちよかった。たぶん、家族はこの世でもっとも美しい絆だ。きっと将大の父は、その印を息子に見せたかったのだろう。
と、そう思ったときだった。突然誰かに肩を叩かれた。誰だ。僕が立ち止まって振り返ると、そこには笑顔のゴッドがいた。
「よう!久しぶり」彼はとても陽気にそう言った……が、次の瞬間だった。僕は自分の耳を疑った。
「ひょっとすると、お前のその頭の傷、何なのかわかるかもしれないぞ」
え?頭の傷?何だそれは。そんなもの、僕は知らないが。
それこそ僕は、頭を鈍器で叩かれた気になった。
<タイトルをクリックすると、関連記事をお楽しみいただけます>
前話 幸せのコンパス 第1話
次話 幸せのコンパス 第3話
■フリーペーパー「コンパス」とは
松本市・安曇野市・塩尻市・山形村を配布エリアとした「中信版」と、長野市を配布エリアとした「長野版」の2種類があります。
フリーペーパー「コンパス」では、ウェブ版に掲載されていない、暮らしに役立つ情報もお楽しみいただけます。
■ フリーペーパー「コンパス」設置場所の検索は、こちらをクリック
■定期配本のお知らせ
コンパスは発刊が 3月 / 6月 / 9月 / 12月の末日、季刊誌です。上記にて無料で配布しております。しかし、場所によっては入手しづらいこともあり、コンパスは多数の読者様のご要望にお応えし、定期配本を始めました。配送料 2,000円/年 にて4回お届けします。
定期配本のお申し込みは、コンパス編集部 0263-87-1798 までお電話いただくかお問合せからご連絡ください。